「器用貧乏」で終わらない。僕が自分だけのキャリアの軸を見つけるまで
「自分は何の専門家なんだろう?」と悩むエンジニアが、『人生の経営戦略』をヒントに自己分析。「変革を定着させ、Time to Valueを高める」という自分だけのキャリアの軸を見つけるまでの思考のプロセスを言語化しました。

はじめに:キャリアの「現在地」に悩む、すべてのエンジニアへ
こんにちは。都内で働く一人のエンジニアです。
今回の思考整理は、名著『人生の経営戦略』を読んだことが大きなきっかけでした。この本で特に感銘を受けたのは、「ビジネスにおけるフレームワークという知見を私生活に持ち込むことで、課題感を構造化し、示唆を得る」というアプローチです。この考え方を自分自身のキャリアに当てはめ、長年感じていた悩みを整理してみることにしたのです。
しかし、いざ考えてみると、悩みは尽きませんでした。
「技術力だけを磨くキャリアに疑問を感じる」
「事業やプロダクトにも関わるようになったけど、何でも屋になっていないか?」
「自分のキャリアを一言で説明できない…」
この記事では、そんな私が自分と向き合い、対話を重ねる中で、自分だけのキャリアアイデンティティを言語化するまでの思考の旅を、忠実に書き起こしてみたいと思います。
1. キャリアの最終目的:僕が本当に目指すもの
『人生の経営戦略』の教えに倣い、まず「何のために働くのか?」という問いを立てました。結婚というライフイベントを経て、私の答えは明確になりました。キャリアは人生の目的ではなく、「ウェルビーイング(より良く生きること)を実現するための手段」である、と。
その上で、まずは今後数年〜十数年を見据えて、私が目指すウェルビーイングを二段階で整理しました。老後まで含めた人生全体の計画ではなく、あくまで直近のキャリアを考える上での方針です。
フェーズ1(短〜中期的):基盤固めの時期
家族が増えることを見据え、安心して子育てができる「時間的・金銭的な安定性」を確保する。
フェーズ2(長期的):挑戦と実現の時期
パートナーの夢も応援できるような、場所に縛られない「キャリア的な余裕」を手に入れる。
この二つの目的が、以降の全ての判断のブレない「北極星」となりました。
2. 僕のキャリア・アイデンティティ:「変革を定着させる」専門家として
次に、「自分は何者か?」というアイデンティティの確立に取り組みました。
提供する独自の価値:「PoCの壁」を越える
これまでの仕事を振り返ると、私の価値は「PoC(概念実証)で終わらせず、本番で活用される仕組みにすること」にあると気づきました。多くのDXプロジェクトが「試して終わり」になる中、私はその先の「定着」までを自分の責任範囲と捉えていたのです。
価値を支える3つの柱:「技術 × ファシリテーション × 定着化」
この独自の価値は、3つの要素の掛け算で成り立っていました。
- 技術(Technology): AWSなどの専門知識。全ての活動の信頼性を支える土台です。
- ファシリテーション(Facilitation): カオスな状況を整理し、合意形成を導く、エンジニアリング思考を応用した対話スキル。
- 定着化(Embedding): 開発した仕組みを業務に根付かせ、成果に繋げるプロセスへの責任感。
キャリアを一言で表す言葉:「Time to Value」を高める
このアイデンティティを、より力強いビジネス用語で表現したのが「Time to Value(価値提供までの時間)を高める」という言葉です。製品がリリースされてから、顧客が実際に価値を享受し始めるまでの時間を短縮する。これこそが、私の仕事の本質でした。
3. 成長戦略:本業と副業のシナジーを最大化する
では、この専門性をどう伸ばしていくか。ここで重要になるのが、本業と副業(個人開発など)のバランスです。
当初は、本業に集中すべきか、副業にも時間を割くべきか悩みました。しかし、私の戦略は**「スキル的なシナジー(相乗効果)を最大化する」**ことに決まりました。
- 収入は本業で確保する: まずは本業で安定した基盤を築きます。副業に短期的な収益は期待しません。
- 副業は「未来への投資」と「実験場」: 個人開発では、本業では使わない新しい技術(Firebase, Flutterなど)に触れ、技術の幅を広げます。これは、将来のためのスキル投資です。
- 抽象的な学びを相互に活かす: たとえ使う技術が違っても、「サーバーレス設計の考え方」「コンポーネント設計の原則」といった抽象的な知見は、本業と副業の間で相互に活かすことができます。副業での実験が、本業での提案の質を高めるのです。
この戦略により、リスクを抑えながら、キャリア全体の成長を加速させることができると考えています。
おわりに:自分だけのキャリア像を描き、明日へ進む
この一連の思考整理を経て、私のキャリア像は明確になりました。
私は「『技術を基盤とした変革の定着化』を専門領域とし、事業のTime to Valueを高めるエンジニア」です。
当初感じていた「中途半端さ」という悩みは、今では「希少な専門性」という自信に変わりました。既存の職種名に当てはまらなくても、ロールモデルが少なくても、自分で自分のキャリアを定義し、道を切り拓いていけばいい。そう確信しています。
この記事が、かつての私のようにキャリアの言語化に悩む誰かの、次の一歩を踏み出すきっかけになれたら、これほど嬉しいことはありません。
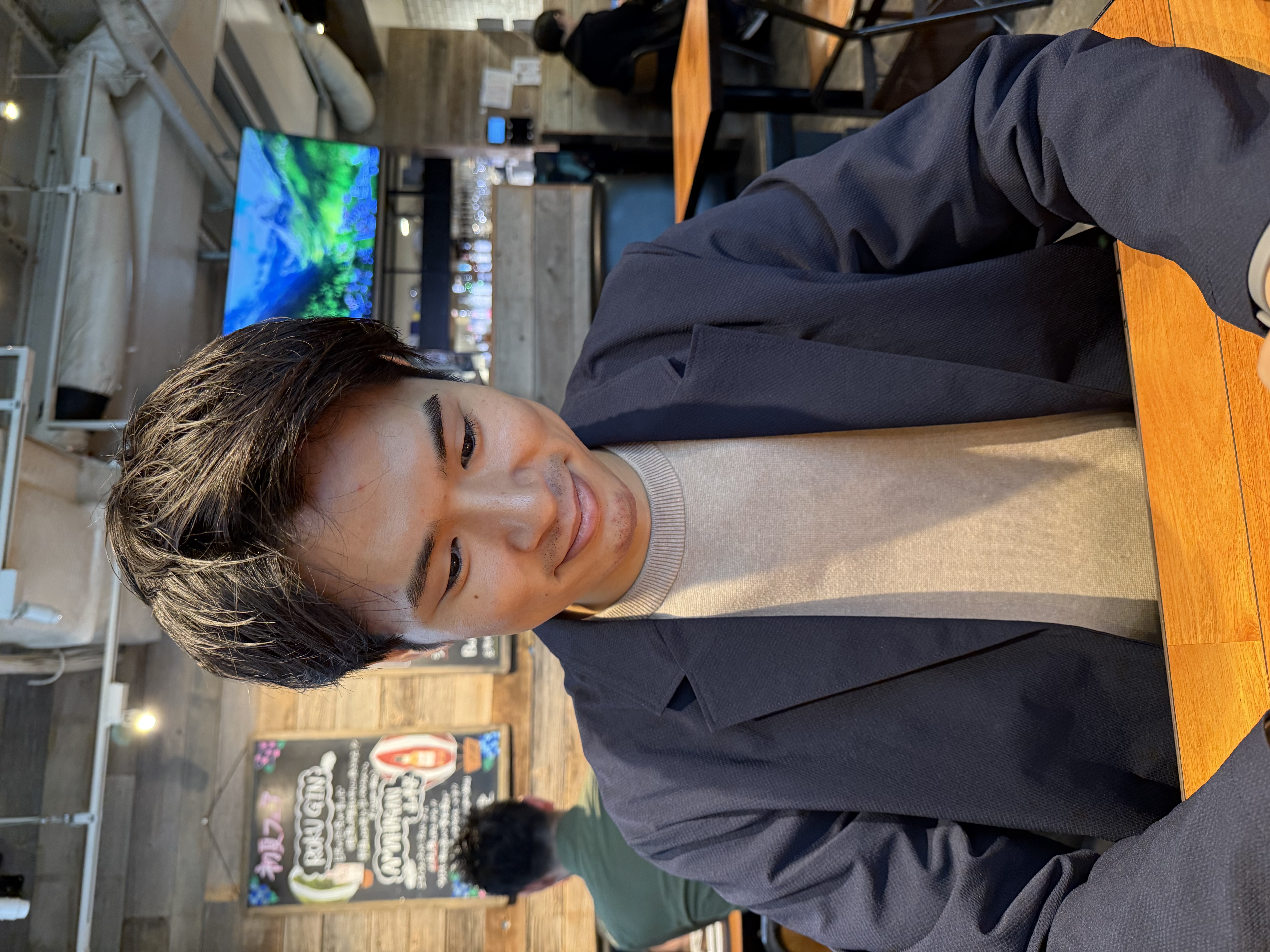
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア
