静かな退職と評価制度、そして僕の生存戦略
静かな退職をきっかけに、人事の立場ならどう制度を設計するかをシミュレーションしながら、自分の生存戦略を考えた思考ログです。

はじめに
最近「静かな退職(quiet quitting)」という言葉をよく目にします。
会社を辞めるのではなく、与えられた業務はきっちりやるが、それ以上の残業や過剰な責任は負わない。つまり「契約範囲内で静かに働く」というスタイルのことです。
これを見たとき、僕はこう思いました。
「もし人事の立場なら、こうした働き方を前提にどう制度を設計するんだろう?」
人事担当ではありませんが、そうやってシミュレーションしてみると、自分の働き方や生存戦略も整理できるのではないかと思ったのです。
この記事は、その思考のログです。
静かな退職とは何か
- 与えられた業務は果たすが、それ以上はやらない
- コロナ以降のワークライフバランス重視の流れの中で広がってきた
- 若い世代ほど「会社に尽くす」より「自分の生活を守る」傾向が強い
怠けではなく「自分を守る」ための働き方。
この考え方が広がっているのは、社会や会社の仕組みが変化している証拠だと感じました。
人事の立場なら、制度をどう設計するか?
ここからがシミュレーションです。
人事の立場に立って「静かな退職を前提にした制度」を考えると、こうなるのではないでしょうか。
1. ベース給与の保障
最低限の業務を遂行すれば、安心して働けるようにする。
👉 「辞めずに続けられること」がまずは組織にとって重要。
2. 成果・挑戦のインセンティブ
モチベーションが高いときに挑戦し、成果を残せばきちんと報われるようにする。
3. 多元的評価
- 成果(数字・納品物)
- 行動(チームへの貢献)
- 成長(スキルアップや挑戦)
これらを組み合わせて評価。最低限だけやる人を即マイナスにせず、公平性を重視。
4. 属人性の緩和
- 360度評価
- キャリブレーション(部門横断の評価調整会議)
👉 上司の好き嫌いで評価が大きく変わらないようにする。
5. チーム単位での評価
個人のモチベーションには波があるため、チーム全体で成果を出せる仕組みを重視する。
人事側からすれば、「全員が常に高モチベで頑張る」ことは期待できない。だからこそ、波を許容する制度設計になるはずだと考えました。
ここから個人の生存戦略へ
このシミュレーションをすると、自分自身の働き方のヒントも見えてきます。
高モチベ期
- 難しい課題や新しいスキルに挑戦する
- 成果を「資産化」する(実績・スキル・ナレッジ共有)
- 周囲に「やるときはやる人」という印象を残す
低モチベ期
- 最低限の責任を守り、信頼を損なわない
- 読書や学習などのインプットで充電する
- 「波があるのは自然」と認識し、無理をしない
長期的なキャリアの見方
- 一時的に頑張れないことがあっても、数年単位で見て成果を積み上げられていれば問題ない
- 高モチベ期に残した成果が、低モチベ期の評価や安心感を支えてくれる
この思考法の意味
僕は人事担当ではありません。
でも「もし自分が人事だったら?」と考えてみると、会社がどう動くかを読む練習になり、その上で「個人としてどう立ち回るか」が見えてきます。
評価制度は完全に公平ではありません。
だからこそ「相手の立場をシミュレーションする」ことで、自分に有利に働かせることができると思うのです。
まとめ
- 静かな退職は怠けではなく、自然な働き方の一つ
- 人事の立場なら「波を許容する制度」を設計するだろう
- 個人としては「高モチベ期に資産を残し、低モチベ期は最低限を守る」ことが戦略になる
- キャリアは「瞬間」ではなく「平均値」で評価される
おわりに(僕自身の感覚)
今回、「人事の立場を想像してみた」ことが、自分にとって大きな学びになりました。
僕は波があるタイプです。だからこそ、
- 高い時に走って成果を残す
- 低い時は安心して守りに入る
このバランスを意識していきたいと思います。
このブログは、そんな自分の思考ログを残す場所。
もし同じように波を感じている人がいたら、この考え方を自分なりに置き換えてみてもらえたら嬉しいです。
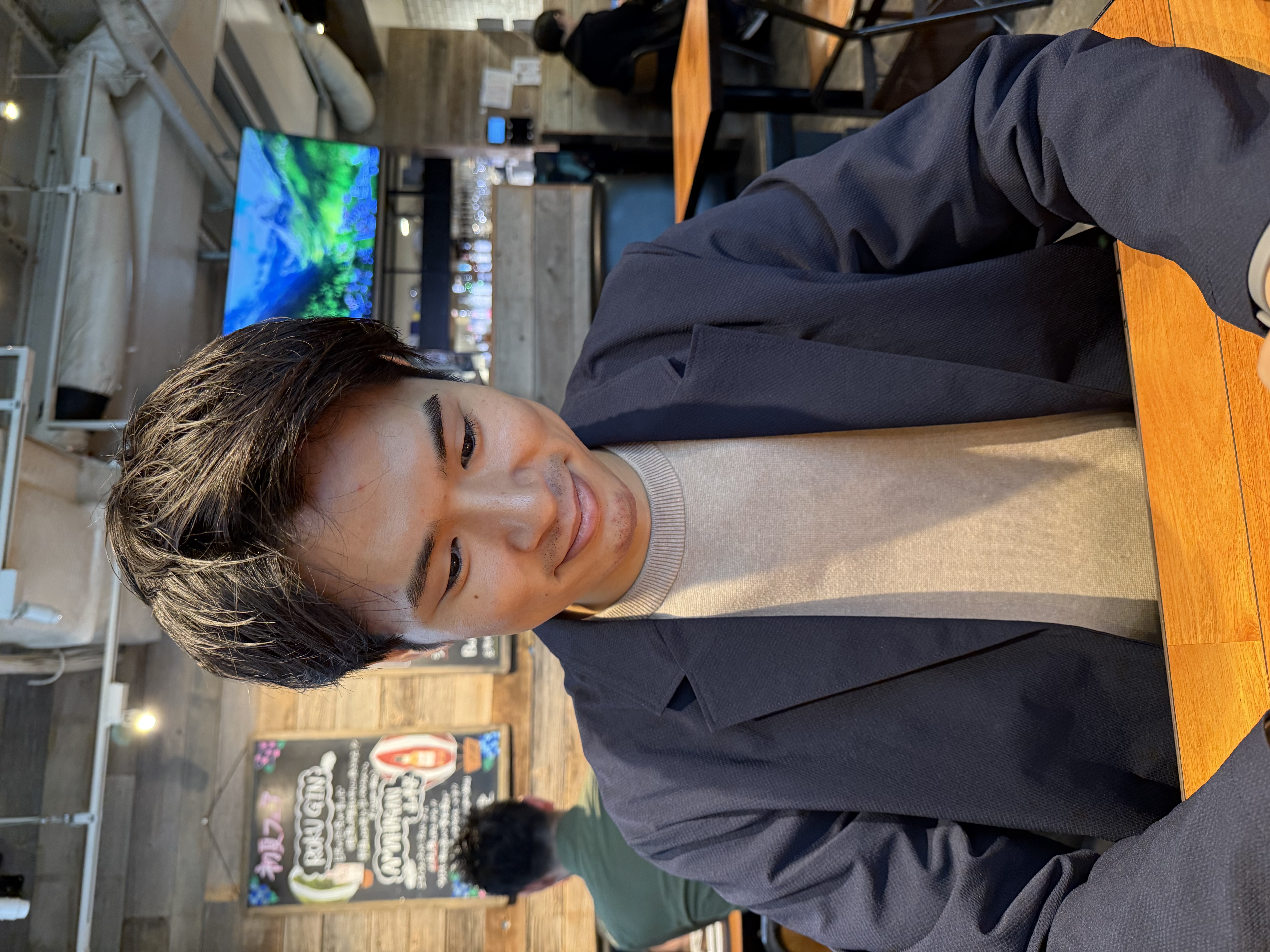
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア
