会計・マーケティング・経営を「重なり」で考える
会計・マーケティング・経営を別々に学んでもつながりが見えない——そこで三つの学問の関係を、自分の立場から整理してみた記録です。
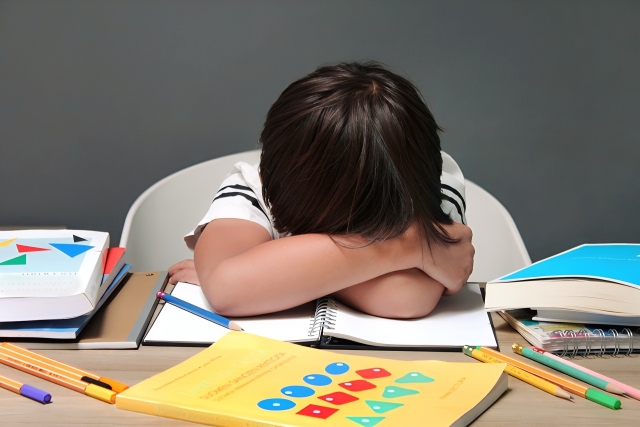
はじめに:なぜこのテーマを考えたのか
僕はマーケティングシステム開発を担当するエンジニアですが、日々の業務の中で「会計」「マーケティング」「経営」という言葉に触れることがあります。
ただ、これらを個別に勉強しようとすると、どうもピンと来ない。
会計は数字だし、マーケティングは顧客や施策だし、経営は戦略全体の話。別々に学んでも断片的で、自分の仕事とのつながりが見えにくい。
そこで今回は、あえて3つの学問を「重なり合う部分」からシミュレーションして考えてみることにしました。
考察プロセス
1. 三者の役割をざっくり定義してみる
- 会計:企業活動を数値化する言語。財務会計は社外向け、管理会計は社内の意思決定向け。
- マーケティング:顧客を理解して、需要を作り出す活動。4Pや顧客体験設計が主な領域。
- 経営:全体最適を考え、方向性を決める意思決定。
2. 相互関係をシミュレーション
- 会計 → 経営:数字(利益率、キャッシュフロー、コスト構造)が意思決定の基盤になる。
- 経営 → マーケティング:どの市場に出るか、どんな顧客を狙うかという戦略がマーケ活動を規定する。
- マーケティング → 会計:施策の成果が売上や利益として戻ってくる。
こう考えると、「独立した学問」ではなく「循環関係」にあることがわかります。
3. MBAという言葉の登場
経営を体系的に学ぶ方法として有名なのがMBA(経営学修士)。会計・マーケ・戦略をすべて横断的に学ぶプログラムです。
ただし、僕が今必要としているのはMBAのような高度で網羅的な学位ではなく、基礎を実務につなげるレベルで理解することだと気づきました。
個人としての気づき
- 学問を縦割りで学ぶよりも、実務で交差する部分を起点にすると理解が進みやすい。
- 特に「会計とマーケをつなぐ指標」(ROIやLTV)は、システム開発をしている自分にとっても身近な切り口。
- 「経営」という言葉は抽象的に聞こえるけれど、結局は「数字(会計)を見て」「顧客(マーケ)を理解して」意思決定することだと整理できた。
まとめ
今回考えてみて整理できたのは次の点です。
- 会計・マーケティング・経営は三位一体で循環している。
- 会計は「鏡」、マーケティングは「市場との接点」、経営は「方向性を決める舵」。
- MBAほど大掛かりでなくても、基礎を「重なり」で学ぶことで、実務に直結する理解が得られる。
おわりに:次の問いかけ
今回は、3つの学問のつながりを自分なりに整理する試みでした。
まだ「学び方」のイメージを描いた段階なので、ここから実際に本を読んで試してみる必要があります。
まずは「全体像をマンガやフレームワークで掴む」ことから始め、そこから会計やマーケティングの基礎に進むのが良さそうです。
次の問いは、「実際に読んでみたときに、どこまで自分の仕事(マーケシステム開発)に結びつけられるか?」。その実感をまた整理していきたいと思います。
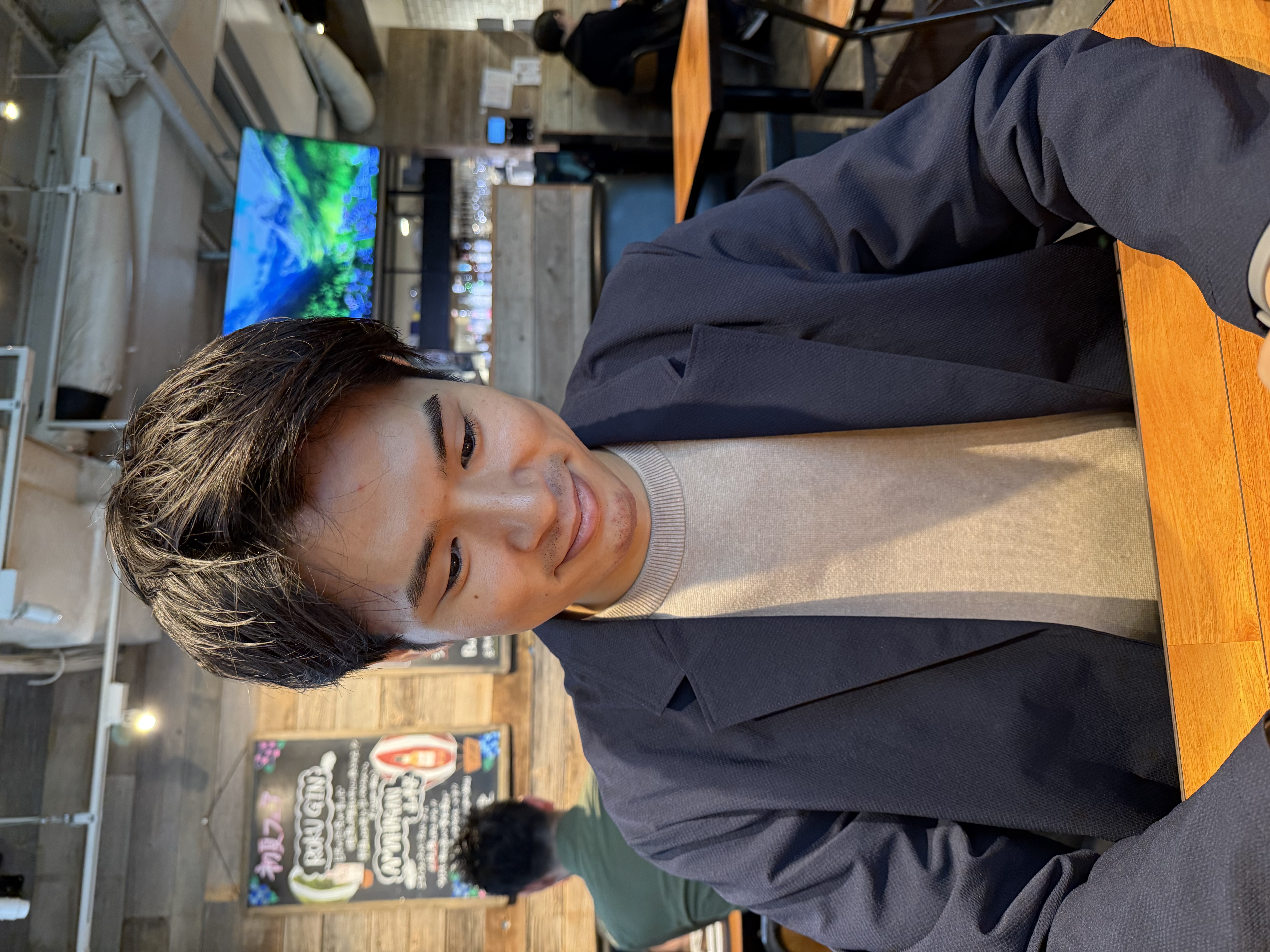
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア
