AIバブルとドットコムバブルを重ねて考える
ドットコムバブルとAIバブルを比較し、善意の失敗と粉飾の違い、Pets.comの構造的な失敗を振り返りつつ、成功事例が投資の熱狂を生む仕組みを考える。

はじめに(なぜこのテーマを考えたのか)
最近「AIバブルはドットコムバブルに似ている」という話をよく見かけます。
ただ僕自身はドットコムバブルをリアルタイムで体験していないため、実態をよく知りません。そこで、歴史を辿りながら今のAIバブルをどう捉えるかを整理してみることにしました。
僕はマーケティングシステム開発を担当するエンジニアで、会計やファイナンスは専門外です。以下はあくまで「シミュレーションして考えてみた」整理であり、読者への解説というよりは自分の思考を残すためのログです。
ドットコムバブルとは?
- 時期:1990年代後半〜2000年初頭
- 背景:インターネットの普及を前に「.com企業」への投資熱が高まり、利益がなくても「未来の成長」だけで株価が上がった。
- 崩壊:2000年を境に株価が急落し、多くの企業が倒産。NASDAQ指数は約80%下落。
- ただし:AmazonやGoogleのように、実際に需要に合致した企業は生き残り、その後社会を変えた。
崩壊の2種類
1. 善意の失敗型(ビジネスモデルが甘い)
- 例:Pets.com、Webvan、eToys、Boo.com
- 特徴:需要やインフラが未熟な中で拡大しすぎ、採算が合わず倒産。
2. 粉飾型(悪意の不正会計)
- 例:Enron、WorldCom
- 特徴:投資家を欺く粉飾を行い、社会全体に大きな打撃を与えた。
👉 「うまくいかなかった理由」と「悪意で騙した理由」は分けて考える必要がある。
Pets.comを深掘り
- 低粗利商品を送料無料で販売 → 利用が増えるほど赤字が拡大。
- 広告費に巨額投資(スーパー・ボウルCMなど)→ 顧客獲得コストが高騰。
- 全国物流を前倒し整備 → 固定費が膨らみ、需要が追いつかない。
つまり「粗利・配送コスト・顧客獲得・固定費」のバランスが崩れていた。
歴史からの学び
- 採算構造を直視すること(ユニットエコノミクス、LTV/CACのバランス)
- 需要とタイミングを読むこと(正しくても早すぎれば失敗)
- 本物は残ること(Amazon、Googleのように基盤を持つ企業)
なぜバブルは繰り返されるのか
- 人の心理:FOMO(乗り遅れ恐怖)、過度な楽観、確証バイアス
- 情報の非対称性:外部から実態が見えにくい
- 資本市場の性質:少数の大当たりがあれば多数の失敗は許容できる
- 技術の不透明さ:難しい技術ほど「魔法」のように見える
👉 バブルは「仕組み上、繰り返される現象」と言える。
生成AIを評価するための3つのレンズ
ChatGPTとの整理を通じて、以下の観点が重要だと分かった。
① 財務(会計・ファイナンス)
- 利用増で利益が出るか?
- CACとLTVは釣り合っているか?
- 継続課金モデルがあるか?
② 顧客(マーケティング)
- 顧客は自腹で使い続けるか?
- 市場や規制のタイミングは合っているか?
- 既存手段より明確に優れているか?
③ 戦略(経営戦略)
- 独自データやネットワーク効果はあるか?
- GPU・電力などの制約をクリアできるか?
- 規模が拡大するとコストが下がる仕組みを持てるか?
おわりに(自分の感覚)
ここまで整理してみて、特に印象に残ったのは「成功事例の存在」です。
ChatGPTやNVIDIAの急成長は「本物」であるがゆえに、その他の多くの企業まで同じ成功ができると誤解されてしまう。実際には新技術をビジネスに繋げられる例は限られているのに、一部の大成功があまりにも大きなインパクトを持ってしまうのだと思います。
ある意味、投資家からすれば「数少ない大当たりを引くために、危ないハズレくじも引く覚悟」で挑んでいるということなのでしょう。そう考えると、AIバブルの混沌もある種の必然なのかもしれません。
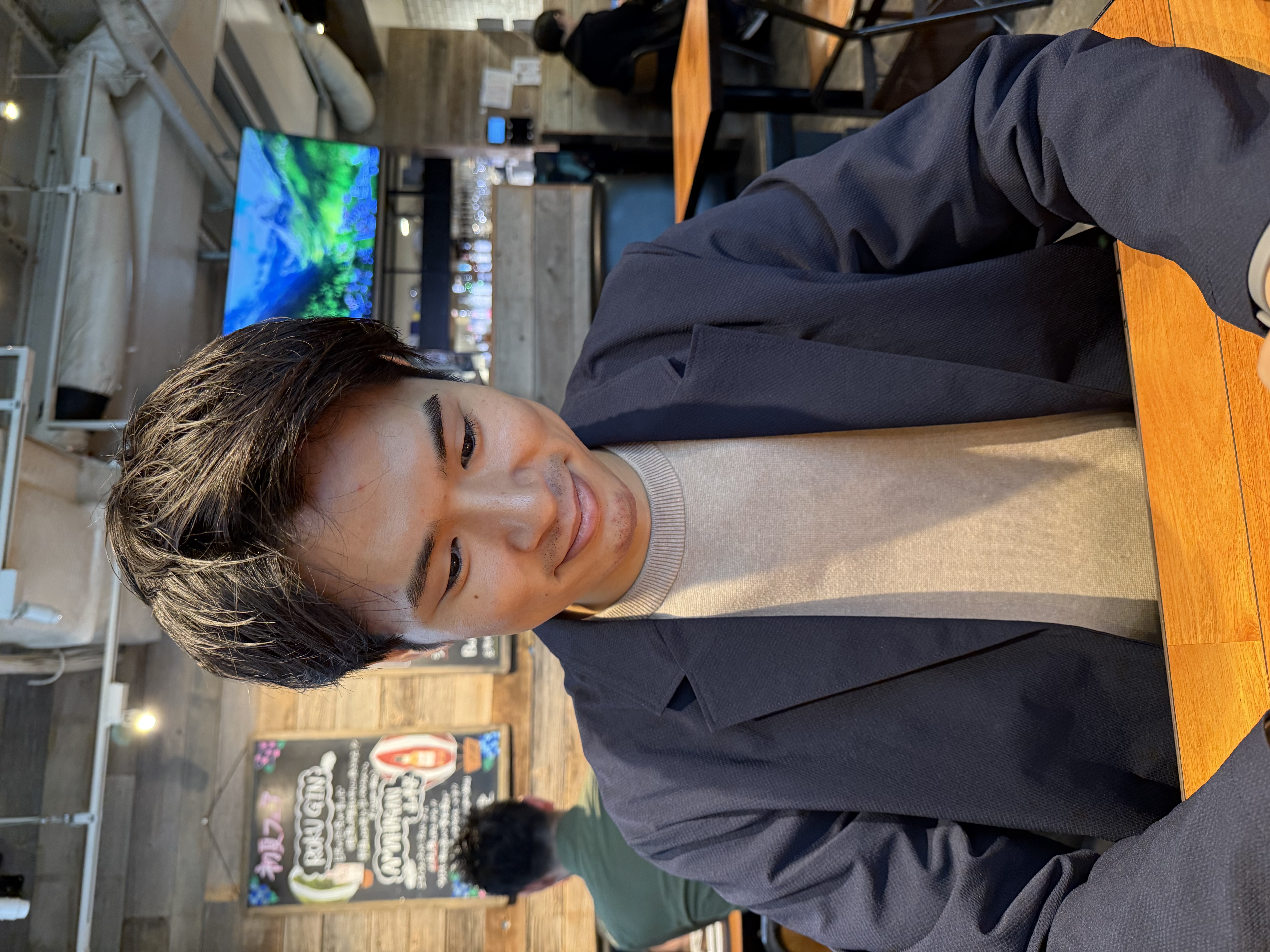
りょう
いろいろなことを考えるエンジニア
